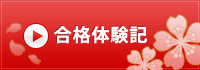現役合格おめでとう!!
2025年 下北沢校 合格体験記

東京大学
理科一類
理科一類
阪野壮真 くん
( 筑波大学附属駒場高等学校 )
2025年 現役合格
理科一類
僕は受験勉強で1番重要なのは問題演習だと思います。世の中ではしっかり理解してから問題を解き、それをしっかり理解した上でより難しい問題を解く方がいいとよく言われています。しかし、僕は電磁気を学んだ時にこれでは通用しないと思いました。電磁気はそもそも出てくる用語が多く、その意味や繋がりやイメージをまず覚えるだけでも大変で、それを実際に問題を解くときに使うというのはとても大変です。僕は電磁気の解説を必死に読んで理解しようと思っていましたが、高校2年生の間は正直チンプンカンプンで、模試では電磁気は0点でした。
僕が電磁気をマスターするときにしたことは、とにかく問題を解くことでした。大学受験で出てくる電磁気の問題はそんなにパターンは多くないので、ひたすら問題を解き解説を読めば、初めは電場と電位の違いも良く分かっていなかった自分でもなんとなく問題を解けるようになっていきました。また、解説を読んでも良くわからないときは苑田先生の授業のノートを見返して復習をしていました。もし勉強に行き詰ったら、初めから全部を覚えてから問題を解くのではなく、解いていくうちに理解していく方向で勉強してみることがおススメです。
次に、東大に受かる上で1番大事なのは過去問演習だと思います。自分がE判定からA判定にあげることができたのは、絶対に過去問演習のおかげだと言い切れます。過去問演習が大事な理由は2つあって、1つ目が試験時間や形式に慣れること、2つ目が過去問から学ぶことが多いということです。
1つ目について、これは言わずもがなといった感じですが、実際慣れによる影響は思ったより大きいです。2つ目が、これは過去問を解く前は気付かなかったのですが、とても重要です。東大の問題に良問が多いということだけではなく、東大で昔出た問題がもう一度似たような形で出されるというのが結構あり、過去問でやった内容をしっかり理解することが大事だと感じました。そのため、僕は過去問をやった後、添削を受け、解説を聞き、全ての問題を解き直して理解の穴を埋めていきました。この時、解き直しをしっかりやったことが自分の力になったと思います。
最後に、僕が東進に通って良かったと思う点は、ある程度自由に決めて勉強できることです。今日は授業を受けるか、授業でやったことを復習するか、問題演習をするか、過去問演習をするか、いつ勉強をするか、全て自分で決めることができます。だからこそ、自分自身でどうやったら合格できるか考え、行動していくことが大事です。後輩の皆さんも、自分で考えて行動し、目標に向かって努力していってください。応援しています。最後に今後の目標ですが、合格したことに慢心せず自分で考えて行動できる大人になりたいです。
僕が電磁気をマスターするときにしたことは、とにかく問題を解くことでした。大学受験で出てくる電磁気の問題はそんなにパターンは多くないので、ひたすら問題を解き解説を読めば、初めは電場と電位の違いも良く分かっていなかった自分でもなんとなく問題を解けるようになっていきました。また、解説を読んでも良くわからないときは苑田先生の授業のノートを見返して復習をしていました。もし勉強に行き詰ったら、初めから全部を覚えてから問題を解くのではなく、解いていくうちに理解していく方向で勉強してみることがおススメです。
次に、東大に受かる上で1番大事なのは過去問演習だと思います。自分がE判定からA判定にあげることができたのは、絶対に過去問演習のおかげだと言い切れます。過去問演習が大事な理由は2つあって、1つ目が試験時間や形式に慣れること、2つ目が過去問から学ぶことが多いということです。
1つ目について、これは言わずもがなといった感じですが、実際慣れによる影響は思ったより大きいです。2つ目が、これは過去問を解く前は気付かなかったのですが、とても重要です。東大の問題に良問が多いということだけではなく、東大で昔出た問題がもう一度似たような形で出されるというのが結構あり、過去問でやった内容をしっかり理解することが大事だと感じました。そのため、僕は過去問をやった後、添削を受け、解説を聞き、全ての問題を解き直して理解の穴を埋めていきました。この時、解き直しをしっかりやったことが自分の力になったと思います。
最後に、僕が東進に通って良かったと思う点は、ある程度自由に決めて勉強できることです。今日は授業を受けるか、授業でやったことを復習するか、問題演習をするか、過去問演習をするか、いつ勉強をするか、全て自分で決めることができます。だからこそ、自分自身でどうやったら合格できるか考え、行動していくことが大事です。後輩の皆さんも、自分で考えて行動し、目標に向かって努力していってください。応援しています。最後に今後の目標ですが、合格したことに慢心せず自分で考えて行動できる大人になりたいです。

東京大学
理科一類
理科一類
三宅潤 くん
( 海城高等学校 )
2025年 現役合格
理科一類
東進に通い始めたきっかけは東進から体験授業の案内のハガキが届いたことでした。兄も東進に通っていたこともあって、体験に行くことにしました。 その時受けた林修先生の授業に感銘を受けました。なんとなく答えらしい要素を本文から抜き出すのではなく、 論理的に文章の構造を分析して、解答の要素を拾っていくという授業スタイルが自分に合うと感じ、他の授業も受けてみたいと思い、入学を決めました。
大学に合格した今、東進で勉強をした1年を振り返って、何が1番効果があったかを考えると、過去問演習講座であると思います。良問揃いの東大の過去問を使って演習をして、復習するときに採点してもらった自分の答案を見つつ、林修先生や苑田尚之先生の授業を受けることができるので、東大の問題に解答するうえで自分に何が足りないのか、何を意識して問題と向き合うべきなのかを考えることができ、得点力を大きく伸ばせたと思います。
また、東進の模試についてですが、共通テスト本番レベル模試は回数が多く、定期的に行われるので、その結果をもとに自分の現在の立ち位置を明確にし、何をいつまでにやるかの計画を立てることの参考にすることができたのはよかったと思います。例えば世界史の場合、自分はインターネットで世界史の勉強法を調べ、模試での自分の点数と照らし合わせて早めに勉強を始めることにしました。10月から一問一答の問題集をやり始める、11月から世界史の参考書の2週目を読む、 12月から参考書と並行して問題集をやるといった具合に計画を立て、実行しました。その結果共通テスト本番ではいい点数が取ることができました。自分が10月から始める判断ができたのは共通テスト本番レベル模試のおかげだと思います。
大学に入学してからは、地球温暖化について学び、その問題を解決するために自分には何ができるのかを探していきたいと思っています。
大学に合格した今、東進で勉強をした1年を振り返って、何が1番効果があったかを考えると、過去問演習講座であると思います。良問揃いの東大の過去問を使って演習をして、復習するときに採点してもらった自分の答案を見つつ、林修先生や苑田尚之先生の授業を受けることができるので、東大の問題に解答するうえで自分に何が足りないのか、何を意識して問題と向き合うべきなのかを考えることができ、得点力を大きく伸ばせたと思います。
また、東進の模試についてですが、共通テスト本番レベル模試は回数が多く、定期的に行われるので、その結果をもとに自分の現在の立ち位置を明確にし、何をいつまでにやるかの計画を立てることの参考にすることができたのはよかったと思います。例えば世界史の場合、自分はインターネットで世界史の勉強法を調べ、模試での自分の点数と照らし合わせて早めに勉強を始めることにしました。10月から一問一答の問題集をやり始める、11月から世界史の参考書の2週目を読む、 12月から参考書と並行して問題集をやるといった具合に計画を立て、実行しました。その結果共通テスト本番ではいい点数が取ることができました。自分が10月から始める判断ができたのは共通テスト本番レベル模試のおかげだと思います。
大学に入学してからは、地球温暖化について学び、その問題を解決するために自分には何ができるのかを探していきたいと思っています。

慶應義塾大学
商学部
商学科
長尾衛 くん
( 高輪高等学校 )
2025年 現役合格
商学部
僕は最初、受験勉強というものを正直舐めていました。「最短の努力をすれば良い大学には行けるだろう」と、根拠のない自信を持っていました。しかし、現実はそう上手くいきませんでした。東進に入ったころ初めて行った模試では、志望校には全く手が届かない位置にいました。第1志望校どころか、ほかの大学もすべてE判定。それが2年の冬のことです。僕は衝撃を受けました。自分はこんなに出来ないのだと、周りの人はもっと先を行っていたのだとその時になって気付きました。
それから、僕は本格的に東進で受験勉強を始めました。自分では全く経験のしたことがない映像による授業に、初めはかすかに不安も覚えていました。ところが、実際に体験してみるとその授業の分かりやすさや面白さに惹かれていき、学ぶことに対するモチベーションが上がっていくのを実感しました。苦手科目の英語を克服し、得意科目の世界史を揺るぎないものにできたのも、この映像による授業の存在が大きかったです。
また、1週間に1度開かれるチームミーティングも重要なものでした。僕のチームミーティングは真面目に勉強の内容を共有したり今後どうすべきかを考えるというよりも、同じ勉強仲間として日々の雑談をして笑いあうものでした。このように定期的にリラックスの時間を設けられたことが長期的な勉強のモチベーションの維持に大きく貢献していたのだと、受験を終えた今振り返って思います。チームミーティングの担任助手の方が合格御守をプレゼントしてくれたことも鮮明に覚えています。その時「僕は1人ぼっちではない」と気付けることが、何よりも嬉しかったのだと、強く実感しました。
東進の共通テスト本番レベル模試は最後まで満足した結果を得られず、目標を遥かに下回る点数を叩き出すたびに何度も落ち込みました。しかしこの模試が、僕の心に反骨心という形で火をつけてくれました。まずどこを間違えているのか、そしてなぜ間違えたのか、さらに次間違えないようにどうすべきか。この3ステップを意識して復習をするごとに自分でも徐々に実力がついていくことを感じました。「間違えた」という事実を飲み込むのは、本当に辛かったです。しかし同時に、「間違えた」という事実を飲み込まなければ前にも進めない。間違えたということに蓋をせず最後まで向き合ったことが、第1志望校に合格した大きな理由の1つであると思いました。
受験勉強はこれで終わりです。そして春から新しい大学生活が始まります。勉強の内容が、今後の役に立つかどうかは僕も分かりません。もしかしたら、一生使わないかもしれません。ところが、「受験勉強を頑張ったという経験」は、決して無駄にならないと確信しています。僕が本格的に受験勉強に取り組み始めたころ、単なる学習以上に日々の自己管理や情報収集などが合否を分けているのだと、目先の勉強ばかりに目を奪われてばかりではダメだと、身に染みて痛感しました。
当然、合格自体にも大きな価値はあります。しかし最後まで粘り強く泥臭く、何があろうと決して諦めずにやるべきことを成し遂げ続けた経験が、僕自身を人間として大きく成長させました。今後の大学生活は新しいことの連続で、慣れないことばかりで不安も伴うと思います。それでも、長い受験勉強を乗り越えて合格を掴み取った僕ならきっと大丈夫だろう。そのように僕は思います。
それから、僕は本格的に東進で受験勉強を始めました。自分では全く経験のしたことがない映像による授業に、初めはかすかに不安も覚えていました。ところが、実際に体験してみるとその授業の分かりやすさや面白さに惹かれていき、学ぶことに対するモチベーションが上がっていくのを実感しました。苦手科目の英語を克服し、得意科目の世界史を揺るぎないものにできたのも、この映像による授業の存在が大きかったです。
また、1週間に1度開かれるチームミーティングも重要なものでした。僕のチームミーティングは真面目に勉強の内容を共有したり今後どうすべきかを考えるというよりも、同じ勉強仲間として日々の雑談をして笑いあうものでした。このように定期的にリラックスの時間を設けられたことが長期的な勉強のモチベーションの維持に大きく貢献していたのだと、受験を終えた今振り返って思います。チームミーティングの担任助手の方が合格御守をプレゼントしてくれたことも鮮明に覚えています。その時「僕は1人ぼっちではない」と気付けることが、何よりも嬉しかったのだと、強く実感しました。
東進の共通テスト本番レベル模試は最後まで満足した結果を得られず、目標を遥かに下回る点数を叩き出すたびに何度も落ち込みました。しかしこの模試が、僕の心に反骨心という形で火をつけてくれました。まずどこを間違えているのか、そしてなぜ間違えたのか、さらに次間違えないようにどうすべきか。この3ステップを意識して復習をするごとに自分でも徐々に実力がついていくことを感じました。「間違えた」という事実を飲み込むのは、本当に辛かったです。しかし同時に、「間違えた」という事実を飲み込まなければ前にも進めない。間違えたということに蓋をせず最後まで向き合ったことが、第1志望校に合格した大きな理由の1つであると思いました。
受験勉強はこれで終わりです。そして春から新しい大学生活が始まります。勉強の内容が、今後の役に立つかどうかは僕も分かりません。もしかしたら、一生使わないかもしれません。ところが、「受験勉強を頑張ったという経験」は、決して無駄にならないと確信しています。僕が本格的に受験勉強に取り組み始めたころ、単なる学習以上に日々の自己管理や情報収集などが合否を分けているのだと、目先の勉強ばかりに目を奪われてばかりではダメだと、身に染みて痛感しました。
当然、合格自体にも大きな価値はあります。しかし最後まで粘り強く泥臭く、何があろうと決して諦めずにやるべきことを成し遂げ続けた経験が、僕自身を人間として大きく成長させました。今後の大学生活は新しいことの連続で、慣れないことばかりで不安も伴うと思います。それでも、長い受験勉強を乗り越えて合格を掴み取った僕ならきっと大丈夫だろう。そのように僕は思います。

慶應義塾大学
理工学部
学門A(物理・電気・機械分野)/物理学科、物理情報工学科、電気情報工学科、機械工学科
高原有加 さん
( 恵泉女学園高等学校 )
2025年 現役合格
理工学部
私は、受験において結果が全てだと思っていました。どんなに頑張ろうと、志望校に合格しなければ意味がないと考えていたからです。しかし、受験が終わった今振り返ってみると、その過程にこそ本当に大切なことが詰まっていたと感じます。ここでは、私が受験を通じて学んだことについて話していきたいと思います。
私が志望校を決めたのは高校2年生の3月と、比較的遅い時期でした。当時の私では足元にも及ばないような大学であり、周囲の大人から反対されることもありました。しかし、挑戦せずに終わりたくはなかったので思い切って志望校を決定しました。他の大学にしていたら絶対に後悔していたので、この決断をできて本当に良かったです。
今から志望校を決めるという人は、自分の学力関係なく、行きたいと思った大学を志望校にするべきです。志望校を決めてからは同じ志望校の人に追いつこうと必死でした。何せ高校3年生の時点でスタートが遅れているので、他の人よりも勉強しなければ間に合いません。
春夏は基礎固め、秋頃から本格的に過去問演習を始めました。春や夏は志望校合格への期待でいっぱいで、勉強が苦ではありませんでした。しかし秋や冬になると自分と志望校との距離が演習によって数値化され、勉強しても伸び悩む点数を見てこのままで本当に受かるのか、と日に日に不安が大きくなっていきました。直前期は不安で夜眠れないことも多々ありました。そんなとき私を支えてくれたのは東進の友人や担任助手の方々でした。
友人とはお互い落ち込んでいるときに励まし合い、担任助手の方には他の人に言えないような不安や葛藤を聞いていただきました。人間、不安な時はその気持ちを口に出すだけでもかなり楽になるので行き詰まったときは信頼できる大人に話してみるのも良いと思います。そんなこんなで共通テストを終え、2次試験までの1ケ月、死ぬ気で追い込みました。
個人的にはこの1ケ月が1番大変だったのですが、周囲の応援のおかげで何とか2次試験も終えることができました。私はこの経験ができて本当に良かったと思っています。それは、受験を通じて忍耐力、計画性、そして何より同じ目標に向かって一緒に努力できる素晴らしい友人ができたからです。大学に入ってからも、この経験を活かして夢に向かって努力し続けたいです。
私が志望校を決めたのは高校2年生の3月と、比較的遅い時期でした。当時の私では足元にも及ばないような大学であり、周囲の大人から反対されることもありました。しかし、挑戦せずに終わりたくはなかったので思い切って志望校を決定しました。他の大学にしていたら絶対に後悔していたので、この決断をできて本当に良かったです。
今から志望校を決めるという人は、自分の学力関係なく、行きたいと思った大学を志望校にするべきです。志望校を決めてからは同じ志望校の人に追いつこうと必死でした。何せ高校3年生の時点でスタートが遅れているので、他の人よりも勉強しなければ間に合いません。
春夏は基礎固め、秋頃から本格的に過去問演習を始めました。春や夏は志望校合格への期待でいっぱいで、勉強が苦ではありませんでした。しかし秋や冬になると自分と志望校との距離が演習によって数値化され、勉強しても伸び悩む点数を見てこのままで本当に受かるのか、と日に日に不安が大きくなっていきました。直前期は不安で夜眠れないことも多々ありました。そんなとき私を支えてくれたのは東進の友人や担任助手の方々でした。
友人とはお互い落ち込んでいるときに励まし合い、担任助手の方には他の人に言えないような不安や葛藤を聞いていただきました。人間、不安な時はその気持ちを口に出すだけでもかなり楽になるので行き詰まったときは信頼できる大人に話してみるのも良いと思います。そんなこんなで共通テストを終え、2次試験までの1ケ月、死ぬ気で追い込みました。
個人的にはこの1ケ月が1番大変だったのですが、周囲の応援のおかげで何とか2次試験も終えることができました。私はこの経験ができて本当に良かったと思っています。それは、受験を通じて忍耐力、計画性、そして何より同じ目標に向かって一緒に努力できる素晴らしい友人ができたからです。大学に入ってからも、この経験を活かして夢に向かって努力し続けたいです。

明治大学
文学部
文学科/日本文学専攻
鈴木健太郎 くん
( N高等学校 )
2025年 現役合格
文学部
僕は、中学時代に勉強を疎かにしていたため、高校生になったときの偏差値は40ちょっとと、お世辞にも勉強ができるとは言えない状態でした。そんな僕でも、二つの活用法で東進を使いこなすことで、明治大学に合格することができました。
一つ目の活用法は、とにかく自習室を利用することです。自習室は、騒音もなく落ち着いて、テーブル周りもパーテーションで区切られている半個室状態なので、問題に集中して取り組める環境になっています。僕は通信制の高校に通っていたこともあり、三年生のときは毎日開校と同時に自習室に向かい、過去問演習を行っていました。
二つ目の活用法は、担任助手の方に積極的に相談することです。担任助手の方は大学生の方がほとんどで、受験の経験値が現役高校生とは桁違いです。自学自習で迷ったときや、勉強に対して不安を抱えているときには、担任助手の方に相談することで、的確なアドバイスをもらえます。また、自分の悩みを誰かに打ち明けることで、モヤモヤが晴れ、スッキリとした気持ちで勉強に臨むことができます。担任助手の方に相談することは、勉強効率を上げることにもつながるのです。
僕は将来ゲームクリエイターになって、世界中の人に面白い遊びを提供するのが夢です。一見、受験や大学での勉強と関係ないように見えますが、受験で培った集中力と、これから大学で経験していく様々な出来事は、ゲーム作りで必要な忍耐力と広い視野を養ってくれることでしょう。
一つ目の活用法は、とにかく自習室を利用することです。自習室は、騒音もなく落ち着いて、テーブル周りもパーテーションで区切られている半個室状態なので、問題に集中して取り組める環境になっています。僕は通信制の高校に通っていたこともあり、三年生のときは毎日開校と同時に自習室に向かい、過去問演習を行っていました。
二つ目の活用法は、担任助手の方に積極的に相談することです。担任助手の方は大学生の方がほとんどで、受験の経験値が現役高校生とは桁違いです。自学自習で迷ったときや、勉強に対して不安を抱えているときには、担任助手の方に相談することで、的確なアドバイスをもらえます。また、自分の悩みを誰かに打ち明けることで、モヤモヤが晴れ、スッキリとした気持ちで勉強に臨むことができます。担任助手の方に相談することは、勉強効率を上げることにもつながるのです。
僕は将来ゲームクリエイターになって、世界中の人に面白い遊びを提供するのが夢です。一見、受験や大学での勉強と関係ないように見えますが、受験で培った集中力と、これから大学で経験していく様々な出来事は、ゲーム作りで必要な忍耐力と広い視野を養ってくれることでしょう。